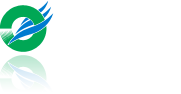公開日 2025年04月30日
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子ども(※)を養育している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
※対象の子ども:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)
支給要件
次の1~9のいずれかに該当する子どもについて、母、父または養育者が監護等している場合に支給されます。
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
4 父または母が生死不明の児童
5 父または母に1年以上遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
7 父または母が1年以上拘禁されている児童
8 婚姻によらないで生まれた児童
9 その他、上記1~8に相当すると認められる場合
◆児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて ※令和3年3月分から
児障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ[PDF:592KB]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html(厚生労働省ホームページ)
〇見直し内容
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等(注1)を受給しているひとり親家庭の方の児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう見直されました。なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注2)の改正はありません。
(注1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
〇手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は原則、申請は不要です。それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。
◆児童扶養手当制度の一部改正について
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されています。
1.所得限度額について
|
所得控除対象 扶養親族等人数 |
本人(請求者) |
配偶者及び 扶養義務者所得 |
|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
2.第3子以降の加算額について
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。
手当の支給額
監護・養育する子どもの数、受給資格者・同居の親族等の所得により決まります。
※手当には所得制限があります
| 区分 | 全部支給されるとき | 一部支給されるとき |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 月 額 46,690円 | 月 額 46,680円 ~ 11,010円 |
|
児童2人以上のとき 児童1人を除いて1人につき |
加算額 11,030円 | 加算額 11,020円 ~ 5,520円 |
◆支給日
奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日に、前月までの2ヵ月分が支給されます。
※11日が土曜・日曜日または祝日のときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。
新しい所得による手当額の変更については、1月支給(11月分)からとなります。
現況届
手当の受給資格者は毎年8月に現況届の提出が必要です。
※現況届の提出がない場合、受給資格がなくなる(手当を受け取れなくなる)可能性があります。
手当額が0円の方も提出が必要ですので、忘れずにお願いします。
届出の内容が変わったとき
次のような場合には、資格喪失または手当額変更となりますので速やかに届出を行ってください。
届出が遅れると支給した手当を返還していただくことがあります。
・婚姻をしたとき(事実婚を含む)
・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき
・受給者、児童が死亡したとき
・拘禁されていた父または母が出所したとき
・遺棄していた児童の父または母から連絡等があったとき
・児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくするようになったとき
・受給者または児童が公的年金等(障害年金、遺族年金、遺族補償など)を受けるようになったとき
・扶養義務者が増えたときまたは減ったとき
・監護する児童が増えたときまたは減ったとき(児童の婚姻等を含む)
・所得の修正申告をしたとき
・その他、支給要件に該当しなくなったとき
虚偽の申告を行って不正に手当を受け取った場合には、児童扶養手当法第23条の規定により受け取った手当を返還していただくことがあります。
また、児童扶養手当法第35条の規定により三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせはこちら
健康福祉部子育て健康課 (輪島市ふれあい健康センター内)
TEL:0768-23-0082
FAX:0768-23-1138
MAIL:kodomomirai@city.wajima.lg.jp
※担当者が不在のことがありますので、来庁される際には必ず事前にご連絡ください。
関連記事
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード