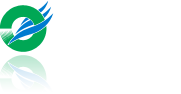公開日 2021年04月01日
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置された広域連合が主体となり、市町と協力して運営しています。
1.対象者
(1)75歳以上の方
→75歳の誕生日から資格を取得します。
(2)65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方
→障害認定申請をして広域連合から認定をうけることが必要です。
※生活保護を受けている方は本制度の対象外となります。
2.マイナ保険証
マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証の利用登録をすることで、マイナ保険証として利用することができ、医療機関の機械で読み取ることで保険診療を受けることができます。
【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナ保険証にはさまざまなメリットがあります
医療機関などを受診される際は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
(1)保険証としてずっと使える
引っ越しをしてもマイナンバーカードを保険証として使うことができます。
※保険者が変わった場合、異動の届け出は必要です。
(2)限度額認定証として使える
限度額認定証がなくても、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。
(3)健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、自分の薬剤情報や健診情報を確認できます。
(4)医療費の事務コストの削減
医療保険の請求誤りが減少するなど、保険者等の事務処理コストの削減につながります。
マイナ保険証の利用登録方法
(1)医療機関や薬局のカードリーダーから登録
難しい操作はなく簡単に登録ができます。
(2)マイナポータルで登録
スマートフォンのアプリやパソコンで登録します。
(3)セブン銀行ATMから登録
3.負担割合
医療機関で受診した時に支払う費用(一部負担金)は、かかった医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)負担です。所得に応じて負担割合などが決まります。
≪所得区分による負担割合≫
| 3割負担 |
現役並み所得者Ⅲ |
同一世帯に住民税課税所得(※1)が690万円以上の被保険者がいる方 |
| 現役並み所得者Ⅱ | 同一世帯に住民税課税所得(※1)が380万円以上の被保険者がいる方 | |
| 現役並み所得者Ⅰ | 同一世帯に住民税課税所得(※1)が145万円以上の被保険者がいる方 | |
|
ただし、次のいずれかの要件に該当した場合は、一般Ⅰ・Ⅱの区分になります。 |
||
| 2割負担 | 一般Ⅱ |
同一世帯に住民税課税所得(※1)が28万円以上の被保険者がいる方で、次の(1)または(2)に該当する方 ※現役並み所得者の方を除く |
| 1割負担 |
一般Ⅰ |
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、区分Ⅰおよび区分Ⅱ以外の方 |
| 区分Ⅱ |
世帯の全員が住民税非課税の方(区分Ⅰ以外の方) |
|
| 区分Ⅰ |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方 |
|
※1 住民税課税所得
総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。
住民税の通知には「課税標準額」と表示されています。
なお、前年の12月31日において世帯主であって同一世帯内に合計所得(給与所得から10万円を控除)が38万円以下である19歳未満の方がいる場合は、住民税課税所得から次の①と②の合計を控除した額で判定します。
①16歳未満・・・1人につき33万円
②16歳以上19歳未満・・・1人につき12万円
※2 その他の合計所得金額
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
≪後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて≫
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
・窓口2割負担導入時に伴う急激な負担上昇を防ぐ目的で、令和4年10月1日から3年間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置は、令和7年9月30日をもって終了となりました。
窓口負担割合見直しについて[PDF:717KB]
【制度改正の趣旨などのお問い合わせ先】
後期高齢者窓口負担割合コールセンター 0120-117-571(厚生労働省)
月~土曜日 9:00~18:00 令和8年3月31日まで
≪関連リンク≫
【厚生労働省HP】令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)
【石川県後期高齢者医療広域連合】窓口負担2割導入に伴う外来の限度額に関する配慮措置
4.医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
初回のみの申請により、高額療養費に該当した月があれば自動的に給付されるため、2度目以降は、改めて申請をする必要はありません。
≪自己負担限度額(月額)≫
| 所得区分 | 外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|
現役並み所得者 Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)✕1% |
|
|
現役並み所得者 Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)✕1% |
|
|
現役並み所得者 Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費ー267,000円)✕1% |
|
| 一般Ⅱ |
18,000円 <年間の上限144,000円>※2 |
57,600円 |
| 一般Ⅰ |
18,000円 <年間の上限144,000円>※2 |
|
| 区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。
※2 年間(8月~翌年7月)の外来(個人単位)の自己負担額の合計が年間上限額を超えた分も支給されます。
申請により、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱおよび区分Ⅰ・Ⅱの方は限度額区分が記載された資格確認書が交付されます。
この資格確認書またはマイナ保険証を医療機関窓口に提示すると、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
| 所得区分 | 事前の手続き | 医療機関・薬局では |
|
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ及び区分Ⅰ・Ⅱの方 |
市役所市民課国保係または各支所・出張所で資格確認書に限度額区分を記載するための申請が必要です。 |
「限度額区分が記載された資格確認書」を窓口に提示してください。 |
|
現役並み所得者Ⅲ及び一般の方 |
必要ありません。(資格確認書の提示で限度額が適用されます) |
「資格確認書」を窓口に提示してください。 |
※マイナ保険証をご利用の方は、手続きなしで区分Ⅰもしくは区分Ⅱが適用されます
≪関連リンク≫
【厚生労働省HP】高額な外来診療を受ける皆さまへ
5.入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)
入院したときの食事代は、1食あたりの標準負担額を自己負担していただきます。
| 所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
| 現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ | 510円(注1) | ||
| 区分Ⅱ | 過去12か月の入院日数 | 90日以内 | 240円 |
| 90日を超える(注2) | 190円 | ||
| 区分Ⅰ | 110円 | ||
(注1)①指定難病患者の方は1食300円に据え置かれます。
②精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した方は、当分の間
1食260円に据え置かれます。
(注2)以前加入していた医療保険で「区分Ⅱ」相当であった期間の入院日数も含めます。
区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に限度額区分が記載された資格確認書が必要となりますので、申請してください。
※マイナ保険証をご利用の方は、手続きなしで区分Ⅰもしくは区分Ⅱが適用されます(長期入院該当の場合は申請が必要です)。
6.療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費の支給)
療養病床に入院する方は、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。
| 療養病床入院時の食費・居住費の標準額 | ||
| 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
| 現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ | 510円または470円 | 370円 |
| 区分Ⅱ | 240円 | 370円 |
|
区分Ⅰ (うち老齢福祉年金受給者) |
140円 (110円) |
370円 (0円) |
※入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、療養病床以外に入院の場合の食費の標準負担額と同額の負担となります。
居住費は、指定難病患者の方は0円に据え置きとなります。
区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に限度額区分が記載された資格確認書が必要となりますので、申請してください。
※マイナ保険証をご利用の方は、手続きなしで区分Ⅰもしくは区分Ⅱが適用されます。
7.高額医療・高額介護合算制度
年間(8月1日から翌年7月31日)の後期高齢者医療と介護保険の自己負担額の合計(高額療養費を除く)が下記の限度額を超えた場合には、申請により払い戻しされます。
≪合算する場合の自己負担限度額(年額)≫
| 後期高齢者医療制度と介護保険制度を合算した自己負担限度額 | |
| 現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
| 現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |
| 現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
| 一般Ⅰ・Ⅱ | 56万円 |
| 区分Ⅱ | 31万円 |
| 区分Ⅰ | 19万円 |
8.特定疾病による治療
下記疾病による高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合は、特定疾病の認定を受けた資格確認書を医療機関窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなりますので申請してください。
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
9.交通事故などで医療を受けるとき
交通事故など第三者の行為による傷病の治療費は、原則として加害者が過失割合分を負担するべきものです。
ただし、この治療を後期高齢者医療制度で受けるときは、広域連合で治療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求することになりますので必ず届出が必要となります。
届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませると後期高齢者医療制度で医療を受けることができなくなることがありますので、ご注意ください。
届出には、マイナ保険証または資格確認書、印鑑、事故証明書(自動車安全運転センターで発行)が必要となります。
10.やむを得ず全額自己負担したとき(療養費の支給)
次のような場合は、いったんかかった費用の全額を支払い、申請により自己負担分を除いた額が支給されます。
・急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき(海外渡航中に治療を受けたものも含みます。)
・医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
・医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
11.訪問看護
医師の指示により訪問介護ステーション等を利用された場合かかった費用を支給します。
※費用の1割または2割(現役並み所得者3割)は利用者の方の負担となります。
12.移送費
病気や怪我で移動が困難な方が、緊急やむを得ず移送された場合に要した費用は申請により払い戻しされます。
※後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限ります。
13.被保険者が亡くなられたとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなられた場合、その葬祭を行う方に対し、申請により葬祭費として5万円が支給されます。
お問い合わせ先
石川県後期高齢者医療広域連合 076-223-0140 (広域連合HP http://www.ishikawa-kouiki.jp/)
市民課保険年金係 0768-23-1124
門前総合支所地域生活課 0768-42-9918
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード